井の中の蛙大海を知らずということわざをご存じでしょうか?
ネガティブな印象のあることわざですが、後に続く言葉があって、それによってはポジティブな意味にも変化することわざです。
| 読み方 | いのなかのかわずたいかいをしらず |
|---|---|
| 意味 | 知識、見聞が狭いことのたとえ。 また、それにとらわれて広い世界があることに気づかず、得意になっている人のこと。 |
| 使い方 | 「海外に留学し、自分は今まで井の中の蛙大海を知らずであったと感じた。思っていた以上に世界は広く、様々な考え方の人がいた。」
「地元じゃ負け知らず、なんて言ってるヤンキーは所詮井の中の蛙大海を知らずだ。」 |
| 類義語 |
|
| 対義語 | 人間到る処青山あり |
| 英訳 | He that stays in the valley shall never get over the hill.(谷の中に住み続ける者は、決して山を越えることはない) The frog in the well knows nothing of the great ocean.(井の中の蛙大海を知らず) |
| 補足 | このことわざのあとに「されど空の深さ(青さ)を知る」と続きます。 |
「井の中の蛙大海を知らず」

[box03 title=”由来”]「荘子」の『秋水篇』の一文より
原文:「井蛙不可以語於海者、拘於虚也。」
現代語訳:「井戸の中の蛙と海について語ることができないのは、虚のことしか知らないからだ。」[/box03]
[chat face=”tameninaruzo2.jpg” name=”ためになるZO” align=”left” border=”blue” bg=”none” style=””]「井の中の蛙大海を知らず」と、直接書かれているわけではないですが、近い意味の文章により「井の中の蛙大海を知らず」と表現するようになりました。[/chat]
「意味」見聞が狭いことのたとえ
井の中の蛙大海を知らずとは
[jin-iconbox02]知識、見聞が狭いことのたとえ。
また、それにとらわれて広い世界があることに気づかず、得意になっている人のこと。[/jin-iconbox02]
「ことわざのイメージ」
- 「見識が狭い」
- 「狭い世界のことしか知らない」
ネガティブな意味
「使い方」思っていた以上に世界は広いが広いとき
[chat face=”naruzou.png” name=”ためになるぞう” align=”left” border=”blue” bg=”none” style=””]「この年になってから海外に旅行に行ってみたよ。」[/chat]
[chat face=”obaasan_face.png” name=”ためになるこ” align=”right” border=”green” bg=”none” style=””]「あらまあ、どうだったかい?」[/chat]
[chat face=”naruzou.png” name=”ためになるぞう” align=”left” border=”blue” bg=”none” style=””]「今まで見たことのないものをたくさん見れたんだ。日本では当たり前なことも当たり前ではなかった。自分は井の中の蛙大海を知らずだったと思ってしまったよ」[/chat]
[chat face=”obaasan_face.png” name=”ためになるこ” align=”right” border=”green” bg=”none” style=””]「そうだね、外国に行くと今まで知れなかったことを知れて、これまでの世界が狭いところだったと感じることもあるよね」[/chat]
この例文のように、「井の中の蛙大海を知らず」とは
「広い世界を知らないため知識が狭い世界だけで完結していること」という意味合いで使っています。
これを参考に下にいくつか例文を載せてあります。
「例文」悪い例&良い例
「今日も自粛ムードで引きこもりで気分は井の中の蛙大海を知らずだ!はやく友達に会いたいな」
「全国大会に出るまで自分のレベルは高いと思っていた。しかし、それは井の中の蛙大海を知らずだった。」
「あの人は地元での武勇伝ばかり話しているけど、井の中の蛙大海を知らずだよね。」
「類義語」井の中の蛙大海を知らず8つ紹介
- 鍵の穴から天を覗く
- 夏虫は以て氷を語るべからず
- 管を以て天を窺う
- 井蛙の見
- 井蛙は以って海を語るべからず
- 天水桶の孑孑
- 夏の虫氷を笑う
- 針の穴から天を覗く
自身が狭いところにいるので広い場所を知らないという喩え(針の穴、管など)
生物(夏の虫)が生きられない季節(この場合は冬ですね)
「知らない世界」とたとえているパターンがありますね。
「対義語」人間至る処青山あり
「井の中の蛙大海を知らず」の対義語を紹介します。
[jin-iconbox03]「人間至る処青山あり」
(にんげんいたるところせいざんあ)[/jin-iconbox03]
意味:故郷ばかりが骨を埋めるべき土地ではない。郷里を出て大いに活動すべきである
例文: 人間到る処青山ありという言葉を励みに、新たな人生の一歩を踏み出す決意をした。
[box06 title=”あわせて読みたい”]人間到る処青山あり[/box06]
「英訳」He that stays in the valley shall never get over the hill.
このことわざをそのまま英訳したものはこちらです。
井戸の中のカエルは大海原について何も知りません。このことわざは20世紀初頭に英訳されたものだそうです。
また、同じ意味を持つことわざはイギリスのもので、このようなものがあります。
[jin-iconbox02]He that stays in the valley shall never get over the hill.
(谷の中に住み続ける者は、決して山を越えることはない)[/jin-iconbox02]
こちらはカエルではなく、人間を用いたことわざとなります。
どちらも自分が住んでいる場所以外の環境のことは知ることができない、という意味になりますね。
井戸と大海という「広さ」の対比が、イギリスのことわざでは
「谷の中」と「山を越えた先」という地理的な違いで対比されていることが興味深いです。
続く言葉「されど空の深さ(青さ)を知る」
狭い世界にとらわれてはいけないという否定的な意味をもつことわざですが、このあとに続く言葉があります。
「されど空の深さ(青さ)を知る」 です。
この言葉はことわざの語源である荘子の『秋水篇』にはなかったので、実際のところいつ付け加えられたフレーズなのかはわかりません。
井戸の中の蛙は海の広さは知らないけれど、青い美しい空を知っているということです。
狭い世界に
他にも、このような言葉が続くとされている説があります。
- 「されど天の広さを知る」
- 「されど地の深さを知る」
空の広さも地の深さも、大きい海の上にいたら知ることができなかったことかもしれません。
海にいれば地面を知ることはできませんし、空を知ることはできるのかもしれませんが、その広さも青い色も井戸の中から見るからより壮大さが分かるのでしょう。
おそらく日本に伝わってきてから付け加えられたという説のあるこの言葉は、
狭い世界にいるからこそ理解を深めることがあることだってある、というポジティブな意味になります。
実際のところ、日本は島国で他国と比べると面積的にも狭い国です。
そのため「狭い世界」のようにも感じることはありますが、
だからといって広い世界より劣るということでもないはずです。
まとめ
井の中の蛙大海を知らずの意味は
「知識、見聞が狭いことのたとえ。また、それにとらわれて広い世界があることに気づかず、得意になっている人のこと。」です。
しかしながらその後に続くフレーズである
「されど空の青さを知る」を付け足すことで、
「広い知識や視野はないかもしれないが、だからこそ知っていることだってある」というポジティブな意味にもなります。
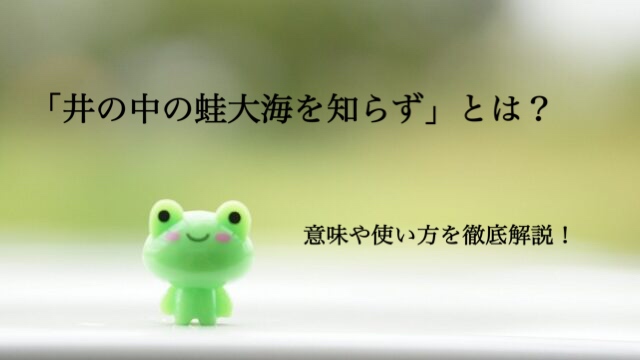
コメント