みなさんは「習わぬ経は読めぬ」ということわざを聞いたことはありますか?
お経と言えば、この前法事があった時にお坊さんが長いお経を何も見ずに読んでいて、どれだけ練習したんだろう?どうやって覚えたんだろう?と気になっていました。
では「習わぬ経は読めぬ」とはどういう意味なのでしょうか?
本記事では、「習わぬ経は読めぬ」という言葉の意味や類義語、使い方など徹底解説していきます。
| 読み方 | 習わぬ経は読めぬ(ならわぬきょうはよめぬ) |
|---|---|
| ローマ字 | Narawanu kyo ha yomenu |
| 意味 | 知識や経験のまったくない物事をやれと言われても、できるものではないということのたとえ |
| 使い方 | 知らないことや経験のないことをやれと言われた時 |
| 英文訳 | ・I can’t read the sutras I haven’t learned
・I can’t because I’ve never experienced it |
習わぬ経は読めぬとは
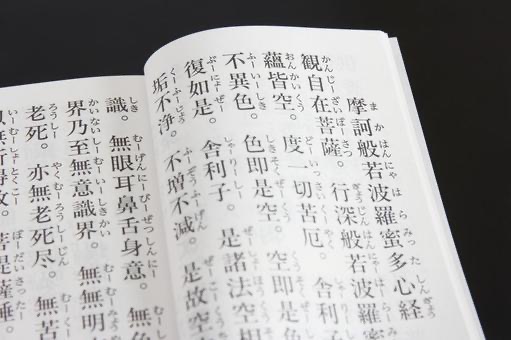
[box03 title=”由来”]
「習わぬ経は読めぬ」は尾張いろはかるたの「な」になります。
いろはかるたは、江戸(東京)・上方(京都)・尾張(大阪)などがあり、地域によって内容が違います。
[/box03]
[box06 title=”あわせて読みたい”]こちらの記事でいろはかるたについて詳しく書いていますので読んでみてください!粋が身を食う(すいがみをくう)の意味とは? [/box06]
「意味」知識や経験のまったくない物事をやれと言われても、できるものではないということのたとえ
「習わぬ経は読めぬ」とは知識や経験のまったくない物事をやれと言われても、できるものではないという意味です。
習ってもいないお経を読めと言われても読めないように、知らないことをいくらやれと言われてもできないことからきています。
「ことわざのイメージ」
「習う」とは教わったことを繰り返し練習して身につけるなどの意味がありますが、このことわざは普段から学んでいることではないので、やろうとしても簡単にはできなかったり、スムーズに出来ないイメージがあります。
[chat face=”22647FB0-00E0-4438-A606-4618282448AB_1_201_a-1.jpeg” name=”お父さん” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]法事でお経を読むとき、お坊さんは本を見ずにスラスラ読んでいるけど、普段お経を読まない僕たちは本を見ないと分からないもんね[/chat]
「使い方」知らないことや経験のないことをやれと言われた時
[chat face=”naruzou.png” name=”ためになるぞう” align=”left” border=”blue” bg=”none” style=””]この前隣の家のなるおさんにケータイの使い方を教えて欲しいと頼まれたんじゃよ[/chat]
[chat face=”obaasan_face.png” name=”ためになるこ” align=”right” border=”green” bg=”none” style=””]なるぞうさんはケータイを持っていないのに使い方が分かるんですか?[/chat]
[chat face=”naruzou.png” name=”ためになるぞう” align=”left” border=”blue” bg=”none” style=””]力になりたかったけど、分からないと言って帰ってきたよ[/chat]
[chat face=”obaasan_face.png” name=”ためになるこ” align=”right” border=”green” bg=”none” style=””]習わぬ経は読めぬですね[/chat]
「例文」悪い例・良い例
「習わぬ経は読めぬ」の例文を見ていきましょう。
意味は、知識や経験のまったくない物事をやれと言われても、できるものではないということのたとえでしたね。
[chat face=”BA029C9C-726B-4928-911F-B7481E81FC90.png” name=”お母さん” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]またこんなに服を泥だらけにして!自分で洗濯してよね![/chat][chat face=”F4DE07CA-8134-4D8C-8C45-BE34EE9DFC61.png” name=”息子” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]お母さん、「習わぬ経は読めぬ」で僕は洗濯は出来ないよ[/chat]
やりたくないことに対して使うのはやめましょう。悪知恵を働かせてはいけません。
「習わぬ経は読めぬ」で外国の方に英語で話しかけられたけど、会話することが出来なかった
「対義語」門前の小僧習わぬ経を読む
「習わぬ経は読めぬ」の対義語を紹介します。
「門前の小僧習わぬ経を読む」
日頃から見たり聞いたりしているものは、いつのまにか覚えてしまうものだという意味です。
お寺の近くに住んでいる子どもは、特に習わなくてもお経を唱えるようになる。幼いころ身近で見聞きしていたことは、特におぼえようとしなくてもおのずから身につくことのたとえ。
[chat face=”22647FB0-00E0-4438-A606-4618282448AB_1_201_a-1.jpeg” name=”お父さん” align=”left” border=”gray” bg=”none” style=””]どっちのことわざも「お経」という言葉が入っていて、ことわざがごちゃごちゃしてきた・・・[/chat]
[chat face=”6CC28441-8541-4204-9032-45194158EE54.png” name=”娘” align=”right” border=”gray” bg=”none” style=””]似ているけど、反対の意味なんだね![/chat]
「英文」2つ紹介
・I can’t read the sutras I haven’t learned
(学んだことのないお経は読めません)
・I can’t because I’ve never experienced it
(一度も経験したことがないので出来ません)
まとめ
ここまで「習わぬ経は読めぬ」について解説してきました。
意味は知識や経験のまったくない物事をやれと言われても、できるものではないということのたとえでした。
経験や知識がないことに、出来ない、分からないとはっきり言えることも素晴らしいことです。しかし、その分からない世界を知ってみることも楽しいかもしれません!
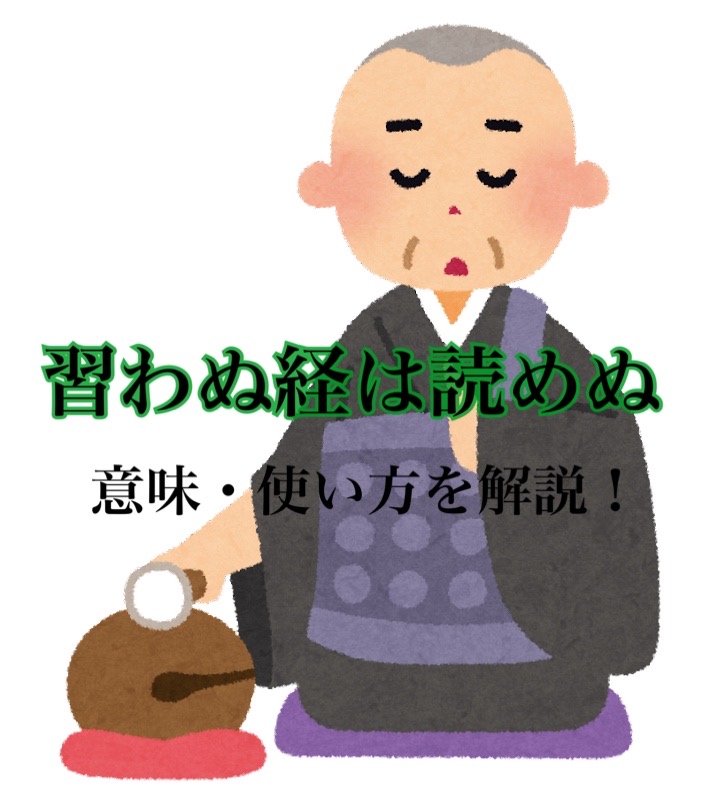
コメント